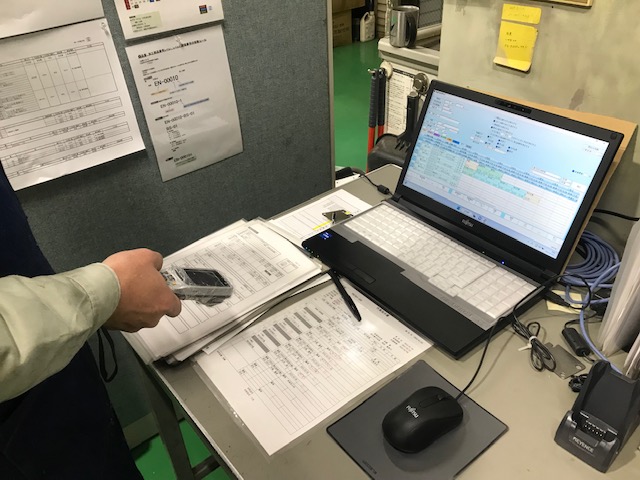店舗や販促の現場で多くの担当者が抱える什器設計に関する悩み。この記事では、実際に寄せられたよくある質問に対して、金属什器の設計者がプロ目線でお答えします。
設計前に知っておきたい基礎知識
什器製作を依頼する前に知っておくとスムーズに進む、基本的な考え方や注意点を解説します。
什器を依頼する際に必要な情報は?
金属什器をオーダー製作する際、設計者に伝えるべき基本情報がいくつかあります。まず最も大切なのは「設置場所の寸法」です。什器は millimeter 単位での調整が求められることが多く、設置予定の床面の広さや天井の高さ、周囲との干渉などを正確に把握しておく必要があります。
次に重要なのが「展示予定の商品情報」。どんな商品を何点陳列したいか、それぞれのサイズ・重量・並べ方などを明確にすることで、棚の段数や耐荷重設計にも直結します。
さらに、「想定する利用シーン」や「搬入経路の条件」もあらかじめ伝えておくと、後のトラブルを防げます。例えば「店頭で頻繁にレイアウト変更がある」「エレベーターに入るサイズで納品してほしい」など、設計初期から共有しておくことで、無駄な試作や修正のコストが削減されます。
標準サイズとオーダーメイド、どちらを選ぶべき?
什器にはあらかじめ用意された「既製品」と、完全に1から作る「オーダーメイド」があります。どちらを選ぶべきかは、主にコストと用途のバランスで判断します。
既製品の魅力はやはり価格と納期です。カタログやECサイトからすぐに選べて、価格も比較的リーズナブル。簡易的な売場や短期キャンペーンなどでは十分なケースも多くあります。
一方で、ブランドイメージを表現したい場合や、特殊なスペースに対応したい場合は、オーダーメイド什器が圧倒的に有利です。自由なサイズ・形状はもちろん、素材やカラーにもこだわることで、空間全体の統一感や話題性を生み出すことができます。
また、当社(三幸製作所)では「セミオーダー」形式も可能です。標準構造をベースにしながら、サイズや仕様のみを変更することで、コストを抑えつつも柔軟な対応ができます。
素材選びで悩んでいます。どう決める?
金属什器の素材選びは、見た目の印象だけでなく、強度や使いやすさ、メンテナンス性にも大きく影響します。
たとえば「スチール」は強度が高く、粉体塗装でカラーバリエーションも自由自在。コストも比較的抑えられ、最も一般的に使われている素材です。一方で、水分に弱いため、湿気の多い場所には向きません。
「ステンレス」は錆びにくく、清潔感のある見た目から医療機関や食品売場でよく使用されます。高級感もある反面、スチールより価格は高めです。
「アルミ」は軽量で持ち運びやすく、イベント什器や仮設売場などによく用いられます。ただし、柔らかいため衝撃に弱い点には注意が必要です。
これらの素材は、必要に応じて「木材」や「アクリル」など異素材と組み合わせることで、デザイン性や機能性を高めることも可能です。用途や売場の雰囲気に合わせて、設計段階から素材を検討することが、満足度の高い什器製作につながります。
よくある設計のお悩みに回答
現場で実際に挙がった質問をピックアップし、設計者の視点から丁寧に回答していきます。
「もっと省スペースに陳列できませんか?」
売場スペースには限りがあります。その中で多くの商品をきれいに並べたいというのは、多くの担当者が抱える共通の悩みです。この課題に対しては、「立体的な陳列設計」や「可動式什器」の導入が効果的です。
たとえば、縦方向のスペースを活用する多段ラックや、スライド式の棚構造を取り入れることで、限られた面積でも商品をしっかり見せることができます。また、背面パネルにフックや棚板を自由に付け替えられる可変式什器であれば、商品ラインナップに応じて臨機応変に対応でき、長期的にも効率的な運用が可能です。
さらに、キャスター付きの移動什器にすれば、必要に応じてレイアウト変更ができるため、イベントや季節ごとの入れ替えもスムーズに行えます。設計段階で「動き」と「変化」に強い什器を想定することが、省スペースかつフレキシブルな売場づくりのカギとなります。
「予算内でインパクトある什器を作れますか?」
「限られた予算でも目立つ什器をつくりたい」という声は非常に多く寄せられます。特に販促什器の場合、視認性やインパクトが売上に直結するため、見た目の演出は妥協できません。
このようなニーズには「部分的な装飾強化」や「素材・構造の工夫」が有効です。たとえば、什器全体を金属で製作しつつ、サイン部分のみをアクリルや木目調シートで装飾することで、コストを抑えつつ高級感やブランドらしさを演出できます。
また、ベースとなる什器は既存設計を流用し、正面パネルだけを変更する「セミオーダー」もおすすめです。当社では、標準型什器の仕様を活かしながら、企業ロゴやカラーリングを組み込むなど、オリジナリティとコストパフォーマンスの両立を図る提案を行っています。
無駄な構造を省き、訴求力を必要な部分に集中させる——それが予算内でインパクトある什器をつくるコツです。
「メンテナンスしやすい什器ってありますか?」
什器は設置後も日常的に使用されるため、メンテナンス性も非常に重要な要素です。特に飲食店や医療現場、頻繁に商品入れ替えがある売場では、掃除や修理のしやすさが什器選びの決め手になることもあります。
例えば、ホコリが溜まりにくい構造や、水拭きできる素材選定は基本です。加えて、棚板がワンタッチで取り外せる仕様にしたり、パーツ交換が可能なモジュール式設計にしたりすることで、店舗スタッフの負担が軽減され、常に清潔で魅力的な売場を保つことができます。
また、キャスターの脱着や配線の隠蔽処理など、細かい部分への配慮も忘れてはいけません。当社では、現場の使用状況をヒアリングしながら、運用後の管理まで視野に入れた設計提案を行っております。
什器は“設置したら終わり”ではありません。使い続ける現場の視点で設計を見直すことで、長く愛用される什器づくりが実現します。
設計段階でのコミュニケーションのコツ
オーダー什器製作をスムーズに進めるために重要な、設計者とのやりとりのコツを紹介します。
図面を確認するときのポイントは?
什器設計の最終段階では、必ず図面(仕様図・組立図)を確認する必要があります。設計者とユーザーの意図のすれ違いを防ぎ、納品後のトラブルを避けるためにも、この作業はとても重要です。
まずチェックすべきは【寸法】です。W(幅)・D(奥行)・H(高さ)の3方向が希望どおりになっているかを確認し、設置場所に本当に収まるか、搬入経路に問題がないかを再確認します。また、棚ピッチや脚の高さなど細かい部分も見落とさず、メモやスケールを使いながら実寸でイメージしておくと良いでしょう。
次に【構造と材質】です。棚板の耐荷重、素材(スチール・ステンレス・木材など)、表面仕上げの種類(粉体塗装・メラミン化粧板など)が設計通りかをチェック。特に食品・医療などの現場では、衛生面や防錆性も重要になるため、仕様記載の有無は必ず確認しましょう。 最後に【組立方法・パーツ構成】も忘れずに。出荷時の状態(組立済み/ノックダウン)、付属品の有無、組立説明書の内容などが明記されているかも重要です。
試作品のチェックポイントは?
什器の品質を最終的に確認するのは「試作品(モックアップ)」のタイミングです。設計通りに機能し、見た目や操作感に問題がないかをリアルに体感できるため、見落としがちな部分まで事前に確認できる貴重な機会となります。
試作品ではまず【実用性】を確認します。商品を実際に置いてみて、陳列のしやすさや取り出しやすさを確認しましょう。想定した商品サイズと合っているか、通行の妨げにならないか、光の反射などもチェックポイントです。
次に【強度・安定性】も試験します。手で揺らしてみてぐらつかないか、棚がたわんでいないかを確認し、特に耐荷重が気になる場合は実際の重量をかけてテストするのがベストです。
また【デザインや印象】も、現物を見ることで初めて気づく点が出てくるものです。色味や質感、ロゴの見え方なども含め、「売場の中で浮いていないか」「ブランドのイメージと合っているか」といった点も重要です。
この段階での気づきは、最終的な改良に直結します。気になる点があれば、遠慮せずフィードバックを設計者に伝えましょう。
納品前にやるべきチェックリストとは?
什器の納品前には、漏れやトラブルを防ぐために「納品前チェックリスト」を使って最終確認を行うことが重要です。現場で「想定と違った」とならないよう、細かく見ておくべきポイントがいくつかあります。
まず【納期・納品先の確認】です。希望した納期に対して出荷スケジュールが合っているか、納品先の住所や受け取り責任者が明確になっているかを確認します。特に大型什器の場合は、時間帯指定やトラックのサイズ対応など、運送条件も確認必須です。
次に【付属品・取扱説明書の有無】です。ネジやキャスター、仕切り板など、什器に必要な部品がすべて揃っているかをチェック。また、組立式の場合は図解入りの取説が添付されているかもポイントです。
さらに【設置作業の有無】についても確認が必要です。「設置・据付をメーカーが行うのか」「現地スタッフで対応するのか」によって、必要な人員や工具も異なってきます。
まとめ
設計の悩みは早めの相談が解決の近道。什器製作を通して店舗の魅力を最大化するためにも、経験豊富な設計者との連携を活かして、理想の売場を形にしていきましょう。
さいごに
什器設計に関する疑問や悩みは、販促・陳列・運用といった多角的な視点から生まれるものです。本記事では、実際によく寄せられる質問に対して、設計者の立場からわかりやすく回答しました。什器は単なるモノ置きではなく、売場の印象や売上を左右する重要な存在です。疑問や不安を一つずつ解消し、納得のいく什器づくりを実現するための一助となれば幸いです。お気軽にご相談ください。